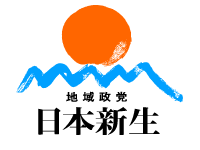小説「廃屋の町」(第32回)
「貴重なご意見ありがとうございます。ところで、こちらのお宅は三世代でお住いでしょうか?」甘木が尋ねた。
「ご覧のとおり、私と主人の二人暮らしです。息子夫婦は仕事の関係で、いま東京で暮らしています。お盆とお正月休みに孫を連れてこの家に帰って来ますが……」女性が言った。
「こんなに立派で広い家で二人暮らしですか。それは寂しいですね」風間が言った。
「この家を建てた当時は家族5人で暮らしていました。30年の住宅ローンも完済して、名実とも我が家になったと思ったら、就職や結婚で息子や娘たちが家を出てしまって、今は私たち夫婦、二人きりの生活になりました」男性が言った
「お二人だけの生活になって、どれくらいになるんですか」甘木が尋ねた。
「もう、10年近くになりますね」男性が答えた。
「息子さん夫婦は、将来、実家に戻る予定はあるんですか?」甘木が尋ねた。
「息子夫婦は、向こうでマンションを買って暮らしていますから、会社を定年退職しても、この家には戻って来ることはないと思っています」女性が言った。
「私は二年前に東京から、家族三人でUターンしてきました。両親は他界して実家は空き家になっていましたが、隣町に住む姉が時々、空き家になった実家に来ては、窓を開けて空気の入れ替えなど、家の管理をしてくれたおかげで、そのままの状態で転居できました」甘木が言った。
「そうですか。この家は建ててから40年近くになりますが、息子たちが孫を連れて戻って来ても、まだまだ使える家です。どっちが先になるか分かりませんが、主人か私が先に介護施設に入れば一人暮らしになります。そして残った一人も施設に入れば、この家は空き家になってしまいます。この家もいずれはそうなるんじゃないかって、主人と話をしています。町内には高齢者だけの家がたくさんありますよ。住む人がいなくなって空き家になった家もあります」女性が言った。
「お休みのところ、いろいろとお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。これで失礼します」と言って、二人は米山家を後にした。
「米山さんの話を聞いて分かったんだけど、米山さんは井上市長の強引な市政運営に対してはあまり良く思っていないようだね」風間が言った。
「一市民というよりは、上司だった井上市長のトップダウンの市政運営を、組織の中から見ていた元職員としての率直な感想だったね。職員だったからこそ見えた井上市政の裏側ということだね。現職の職員は井上市長のことをどういう風に見ているんだろう。興味があるよ」甘木が言った。
「同級生に市の財政課長をやっている杉田昇がいるから、今度、声を掛けて、その辺の話を聞いてみようか?」風間が提案した。
「それはいい考えだね。財政課長なら公共事業の予算執行についても詳しいんじゃないかな」
甘木が言った
「俺たち中学の同級生が甘木を市長選挙に担ぎ出したことは井上市長も知っている。この前、用事があって市役所のロビーで杉田とばったり顔を合わせた時、『最近、総務部長の視線を強く感じるようになった』って、小声で俺に話してくれたよ。どうやら市役所にいる俺たち中学の同級生が監視されているようだ。もしかして、観光振興課長の木下信行も監視されているかも知れないね」風間が言った。
甘木と風間はこの住宅街を歩いてみて、子供のいる家が少ないということが分かった。子供のいる家であれば、子供用の自転車や遊び道具が玄関に置いてあったり、子供の服が外に干してあったりするが、そういった家は少ない。高齢者だけの世帯が多いようだ。どういう事情があって空き家になったかは分からないが、まだまだ使える家もある。子育て世帯にこれらの空き家を提供すれば、住宅街の高齢化もある程度は食い止められるのではないかと甘木は考えた。
(作:橘 左京)