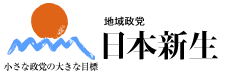小説「廃屋の町」(第40回)
「『農家のため』に行われている土地改良事業が、実際は、土地改良区のため、建設業者のために行われているんじゃないかって思っているよ」
「どういう意味ですか?」甘木が尋ねた。
「土地改良事業は土木工事が主体となる公共事業だけど、この工事を請け負う中小の土木業者が農村部に集中しているんだ。この集落にも青木建設という小さな土木業者の本社事務所がある。これら農村部にある土木業者の多くは農業と兼業でやっているが、なかには農地は持っているが耕作をしない『土地持ち非農家』の業者もいるよ。青木建設は農家もやっているけどね。それに社長の青木敏夫は土地改良区の理事をやっているよ。農村部にあるこれら中小の土木業者と土地改良事業が密接に関係しているんだ」
「関係しているって、どういうことですか?」甘木は尋ねた。
「農村部にある中小の土木業者は規模の小さな土木工事であれば直接請け負うことができるんだが、工事の規模が大きくなると大手の業者が受注して、工区に分けられ小さくなった工事を、中小の業者が下請や孫請けで請け負っているんだ」
「青木建設は下請けや孫請けで受けている工事が多いんですか?」甘木が尋ねた。
「そうだね。利幅が少ないって社長がぼやいているけどね。土地改良事業の工事は稲刈りが終わった後に始まって、翌年春の田起こしまでの間に行われるんだけど、この時、農閑期に入った農家が土木作業員として雇われているんだ。私も青木建設の仕事を手伝ったことがあるけどね」
「土地改良事業って、農家の冬場の仕事を提供しているんですね。農家にとってはいいことじゃないですか」風間が言った。
「確かに、専業農家は農協に米を出荷すれば春まで仕事はない。農家にとっては冬場も仕事があるというのはありがたい話かも知れないが、これって土地改良事業で農作業が効率化されて、余剰になった時間を使って農業以外の仕事をして農家の年間所得を増やしてくれ、という話じゃないか。農作業が効率化されても、米の収量が増えるわけではない。農業収入が増えないのに、事業費の一部を農家が負担するため、逆に経費の方は増えてくる。その結果、農業所得が減ってしまう。減った分を補填するために、農家が土木作業員として冬場に働くというのは、矛盾していると思うけどね。もちろん、農家にとって必要性の高い土地改良事業もあるけど、そこまでしなくてもいい事業もあるよ。さっきも言ったように、土地改良事業の中には、農家のためというよりは、土地改良区のため、建設業者のために行われている事業も多いと思っているよ」
「おっしゃるとおり、矛盾していますね。工業生産を例にして考えるとよく分かります。工場や機械設備などの生産設備への投資は、生産性を引き上げ、また付加価値の高い製品を作って、売り上げを伸ばすために行われます。一方、土地改良事業は作業効率が上がっても、米の収穫量が増えるわけでもないし、品質のよい米ができるわけでもありません。作業効率が上がって余剰になった時間を使って、減った農業所得の穴を農業以外の所得で埋めるというのは、確かに矛盾した考えですね」甘木は言った。
「土地改良事業でもう一つ矛盾した話があるんだ」
「それは、どんなことですか?」甘木が尋ねた。
(作:橘 左京)